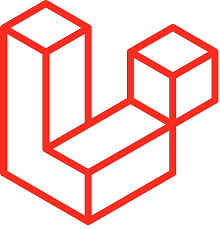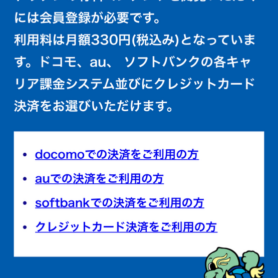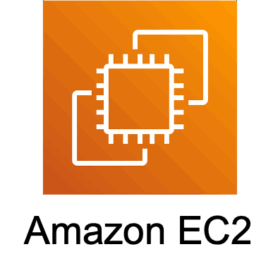AWSコスト見積もりの盲点:リセラー契約で無料枠が消える理由とその対策
はじめに
AWS(Amazon Web Services)は、クラウド基盤として幅広く利用されており、その豊富なサービス群は非常に魅力的です。 このサイトでもAWSを活用したサービス構築の記事を取り上げており、実際に私たち自身のサービス提供にもAWSを利用しています。
AWSの利用を開始するには、公式サイトから利用申請を行い、ユーザー情報とクレジットカードを登録すれば、すぐに利用を開始できます。 一方、法人での利用においては、AWSのセールスパートナーを経由して契約するケースもあります。これは、Cloudpack(アイレット)やクラスメソッドといったAWS公認の請求代行パートナー(リセラー)を通じてAWSアカウントを発行・管理する方式で、以下のようなメリットがあります。
- 毎月、日本円建ての請求書を発行してくれるため、会計処理が楽になる
- 支払いに対して数%(3〜10%程度)の割引が適用されることがある
- 本来は有償となるAWSサポート(Businessサポート以上)を、パートナー経由で間接的に利用できる
- 各種リソース制限緩和申請の際に、パートナーの信頼性が後押しとなることもある
これらのメリットを見れば、AWSを利用する場合は常にこれらのリセールパートナーと契約するべきと考えるかもしれません。 しかし、もしあなたが単に「今よりコストが安くなるから」ということだけを理由にリセラー契約を利用する場合は注意が必要です。 なぜなら、支払いの割引を適用したとしても、普通に利用するよりもコストが高くなるケースが存在するためです。
この記事では、そのような AWS コスト見積の落とし穴がなぜ発生するのかについて説明します。
リセラー契約でAWSの利用コストが下がる理由
AWSのリセラー契約を利用すると、通常よりも利用コスト3~10%程度下がることが紹介されています。この背景には、大きく2つの仕組みが関係していると考えられます。
ひとつは、AWSがリセラー向けに提供している特別な契約に基づく割引制度です。AWS公式にも「リセラーとしてAWSを再販するプログラム」が存在しており、対象となるパートナー企業は、一般利用者とは異なる条件でAWSサービスを提供できる契約を結んでいると考えられます。
もうひとつは、AWSの課金体系が利用量に応じて単価が下がる「ボリュームディスカウント」を採用している点です。 たとえば、CloudFront のデータ転送コストは、月間の利用量が多くなるほど単価が下がる「階段式料金体系」を採用しています。公式料金ページによると、日本リージョンの場合、最初の10TBまでは $0.114/GB ですが、5PB(5,000TB)以上のトラフィックが発生する場合、その単価は$0.06/GB にまで下がります。
AWSでは「Organizations」という仕組みを使って、複数アカウントを1つの統合請求単位にまとめることが可能です。 リセラーはこの仕組みを使って多数の顧客アカウントの使用量を合算し、全体の使用量合計を押し上げることで、より低単価の課金帯を適用させることができます。そのうえで、得られた割引の一部をエンドユーザーに還元する形で、利用料金を引き下げていると考えられます。
アカウントの統合と無料枠の関係性
AWSアカウントには「無料枠(Free Tier)」という仕組みがあります。 この無料枠には大きく2種類あり、ひとつはアカウント開設から一定期間(通常12か月間)だけ有効なもの、もうひとつはアカウントを利用している限り継続的に有効なもの(恒常無料枠)です。
前者の例としては、EC2の「t2.micro」インスタンスの無料利用枠が挙げられます。後者の例には、CloudFrontのデータ転送コストや、AWS LambdaやDynamoDBといったサービスに対する常時無料枠が含まれます。 実際の運用や見積もりの場面では、期間限定の枠よりも、後者の恒常的な無料枠の有無を考慮することがより重要です。
主な恒常無料枠と、それを通常利用した場合の課金相当額は以下の通りです(いずれも東京リージョン相当、2025年時点の目安)
- CloudFront:データ転送 1TB/月(アウトバウンド) ≒ 114 USD
- Amazon Cognito:アクティブユーザー5万/月(ユーザープール) ≒ 275 USD
- AWS Lambda:100万リクエスト+40万GB-秒の実行時間 ≒ 7 USD
- DynamoDB:ストレージ25GB ≒ 7.125 USD
このように、無料枠が適用されなければ、通常運用でも100USD以上の月額コストが発生しうるサービスが含まれています。それにも関わらず、これらを継続的に無料で利用できるのが恒常無料枠の大きなメリットです。
しかし、ここで注意すべき点があります。 これら恒常的な無料枠は「AWS Organizations 単位」で1アカウント分のみ適用されるという仕様です。つまり、Organizationsに複数のAWSアカウントを統合すると、それぞれのアカウントに個別に無料枠が割り当てられるのではなく、組織全体で1枠分だけが共有されることになります。
その結果として、リセラー契約や統合請求によってアカウントがOrganizationsに所属した場合、紐づけられた各アカウントの無料枠が実質的に失われます。この仕様は、小規模サービスの運用や、検証用アカウントを複数立てて運用しているケースでは特に影響が大きく、想定外の課金発生につながります。
無料枠が活用できなかったことでコストが発生した実例
前述の通り、AWSを利用する前提として「無料枠を活用するつもりでシステムを設計」していたにもかかわらず、リセラー経由で提供されるAWSアカウント(=統合請求が適用されるアカウント)を使用したことで、本来想定していた無料枠が適用されず、思わぬコストが発生するというケースに実際に遭遇しています。 以下は、実際に経験した具体的な事例です。
ケース1:CloudFrontの無料枠が利用できず、月額コストが倍増した
ある小規模なウェブサイトを運営するにあたり、リセラー経由でAWSアカウントを取得しました。 構成はEC2インスタンス1台に加え、CloudFront経由で画像などの静的コンテンツを配信する形です。データ転送量は毎月およそ700〜800GB程度でした。
EC2インスタンスおよびEBSボリュームの利用料は、概算で月40〜60 USD程度に収まっていましたが、CloudFrontのデータ転送コストだけで毎月およそ90 USDが課金されてしまいました。 結果として、全体の月額は150 USD前後となり、ここからリセラー割引(10%)を受けたとしても最終請求額は約135 USDに達しました。
一方、CloudFrontには毎月1TBまでの恒常的な無料枠が用意されており、これが適用されていればデータ転送料金は発生しなかったはずです。 つまり、無料枠を活用できていれば、EC2関連コストだけで済み、割引がなくとも60 USD程度に抑えられたと考えられます。
ケース2:Cognitoの無料枠消失による追加コストの発生
別のプロジェクトでは、ウェブサーバーのID管理基盤としてAmazon Cognitoを採用しました。 アクティブユーザー数は月2,000〜3,000人程度であり、Cognitoに用意されている5万ユーザーまでの恒常無料枠を考慮すれば、当初は「無料で運用可能」と見積もっていました。
しかし、こちらも対象サービスをリセラー経由アカウントで運用したため、Cognitoの無料枠が適用されず、結果として月額約15 USDの課金が継続的に発生することになりました。 全体からすると、大きな額ではありませんが、無料で使えるという前提が崩れたことで、「これなら最初から Cognito を使わなければよかったのでは?」という見直しと、無料枠の正しい理解の必要性を感じました。
まとめ
AWSアカウントのOrganizations統合については、日常的に意識することは少ないかもしれません。 しかし、その仕組みや契約形態によっては、本来利用できるはずだった無料枠が適用されなくなる可能性があることを、ここまでの実例を通じて見てきました。
特にCloudFrontやCognitoのように、恒常的に無料枠が用意されているサービスであっても、統合請求の影響でその枠が有効にならない場合があるという点は、見落とされがちな注意点です。
今回は、こうした無料枠の消失(および、無料枠利用を前提とする見積)によって発生するコストのインパクトに焦点を絞って紹介しました。AWS自身も専用ページを設けて無料枠を大きく打ち出しており、初期設計段階で「無料枠ありき」の構成を考えるのは、ごく自然なことだと思います。
なお、この記事はリセラー契約そのものを否定するものでは決してありません。 サポート体制や請求の一元管理といった面では多くのメリットがあります。 重要なのは、リセラー契約の導入にあたって、目先のコストダウンに捕らわれるのではなく、その仕組みが無料枠や課金にどのような影響を与えるのかを正しく理解し、運用方針に合った選択をすることです。
この記事を通じて、その判断材料の一助になれば幸いです。